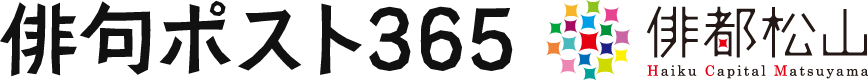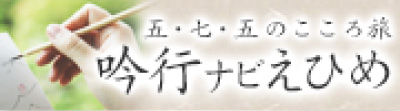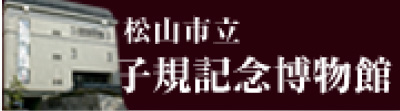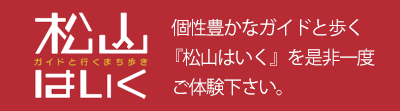兼題「氷柱」に関するお便りを紹介します。
**********************
●季語六角成分図「氷柱」より。(視覚)光、透明、水滴、泡、雪、星、月、青空。軒下、屋根、枝、崖、岩山、銅像、藁人形、仏像、水車、鶏小屋など。(嗅覚)ほぼなし。(聴覚)水の垂れる音。氷の折れる澄んだ高い音。(触覚)冷たい、溶ける、払う、折る。(味覚)子供はなめちゃうかも。(連想力)雪国、北国、みちのく。朝晩の冷え込み。囲炉裏の暖かさ、家庭。重力、引力。★角川歳時記には、「水の滴りが凍って棒状に垂れ下がったもの。軒端や木の枝、崖などに見られる。(以下略)」とあります。『基本季語五〇〇選(山本健吉)』には、氷柱とは古くは張りつめた氷のことで、今で言う「つらら」のことは古くは「垂氷(たるひ)」と呼んでいた、とのことです。ちなみに角川歳時記では地理の分類、『基本季語五〇〇選(山本健吉)』では気象の分類になっていました。★視覚、触覚が強く、美しい光が似合う季語であり、一方で冬の厳しい寒さの象徴のような季語でもあります。氷柱ができるには、ある程度の降雪があり、寒暖が繰り返されることが必要ですので、その意味から地理の季語なのでしょう。北国にお住まいの方は見慣れていらっしゃるでしょうが、私が住む地域ではほとんど見かけません。★好きな句「みちのくの星入り氷柱われに呉れよ 鷹羽狩行」「大空に根を張るつららだと思へ 櫂未知子」/碧西里
***********************
※たくさんのお便りありがとうございます♪ 皆で楽しく読ませていただいています。
写真タイトル:白猪の滝